社会から一区切りつく定年後や、その準備として、新たな趣味として農業を始める人が増えています。
自分の手で作物を育てる喜びがあり、日々の生活に生きがいを持つことができ、
体を動かし、五感を使うことで、若々しさを保ち、健康維持にも繋がります。
心身を豊かにする趣味としての農業です。
場所や土を準備し、種や苗を植えて、水やりなど世話して、成長を見ながら、収穫する。
そのサイクルの中で、生命の不思議さを感じながら、先代からの知識や技術を学びます。
そして、地道な努力が実を結ぶとき、それまで経験したことがない喜びを感じることができるのです。

今年(2025年)の6月、人生初の野菜づくりを始めました。
「何か手を動かす新しいことがしたい」
「自給自足を目指したい」
「とれたての野菜を食べてみたい」といった動機で、まったくの初心者でした。
目次
野菜づくりのメリット
生きがい
育てる喜び
自分の手で作物を育て収穫する喜び…これは新たな生きがいになります。
べつにだれと争うわけでないので、
自分の目で、順調に成長しているか、虫の被害はないかなど、
確かめたり、調べたりしながら、試行錯誤することで、日々の充実感があります。
朝起きて水やりをして、昼に葉の様子を見て、夕方にはまた確認。
種をまいたり苗を植えた後、毎日のように変化していく植物の成長を見守るのは、
子育てのようでもあり、新しい生命が育つ奇跡と、育てる喜びがあります。
農業で心身をリフレッシュ
心を豊かにストレスフリー
適度な農作業は、日光を浴びることでビタミンDの生成を促し骨を強くし、
外で体を動かすことで、体力維持、睡眠の質も向上し、健康で活動的な日々を送ることにつながります。
朝夕の水やりや草取りなど、自然の中で体を動かす習慣が、
生活にリズムを生み、日々の充実感になります。
特に、一日中、机に座ってパソコンをにらんでいた生活だった方には、
土に触れ、自然の中で作業をすることは心のリフレッシュにもつながります。
自分で育てた野菜を食べる喜び
自分の手で育てた野菜の味は格別、大きな満足感を得られ、
旬の野菜を育てることができるため、食に対する意識を高め、料理への興味にもつながります。
自家栽培による食材は新鮮であり、無農薬・減農薬で育てた場合、体に優しい食事となります。
家族で、水やりをしたり、収穫を楽しんだり、料理に使ったりすることで、
家族との新しいコミュニケーションの場にもなります。

野菜づくりの知識やスキルを学ぶ楽しさ
野菜の栽培方法、水やり、肥料、種まき、虫よけ対策、農具の使い方、収穫時期など、
覚えることが山ほどあり、日々新しい発見があります。
そして、実践を通じて、うまくいく時、失敗する時など経験しながら、スキルが身についていきます。
自分に合ったペースで楽しむ
ある程度、自分のペースで取り組み、楽しむことができる点も魅力です。
天候や体調に合わせて無理をしないで進めることが重要です。
一日に、長くても2時間程度にして、頑張りすぎないようにするほうが、長続きします。
野菜づくりの始め方
〇農業塾などで、基礎を学習し、実習する。
(農業アルバイトや農業ボランティアで経験を積む方法もあります。)
①ホームセンター・専門店や経験者に、育て方を聞きながら「家庭菜園」を始める。
②教えてもらえたり、農具を貸してくれる経験者がいる場合は、市町村などの「市民農園」を借りて始める。
③民間のサポート付き「レンタル農園」でアドバイザーに教えてもらいながら始める。

知識も経験もゼロなので、
まず、市の広報誌で知った「農協(JA)の農業塾」に入り、基礎から勉強と実習を始めました。
同時に、経験者の方に教えてもらったり、YouTubeやブログ、図書館でも調べながら家庭菜園からスタートしました。

家庭菜園
家庭菜園は、ベランダや庭で、小さなスペースから始めることが出来ます。
何を育てるか、どう育てるか、何が必要かなど、経験者の方に教えてもらったり、YouTubeなどで調べ
ホームセンターや専門店で聞きながら、種や苗、土や肥料、プランター、スコップ、支柱などをそろえて、スタートできます。
ベランダのプランター栽培といっても、水やり、虫対策、日差しや寒さ対策など、本来の農業と同じですので、将来、農園を借りて栽培するときにも役立ちます。
なお、マンションだと、ベランダを使用できる規約か、排水溝が詰まらないように掃除するとか、注意が必要です。
プランター
プランターは、畑と違って土が乾きやすく、特に暑い時期はまめな水やりが必要です。
底に水がたまる空間のあるプランターは、水やりの回数が少なくてすみ、多少、留守にしても大丈夫です。
土
いろいろな種類の土を混ぜる必要なく、あらかじめ混合されているので開封してそのまま使える
“野菜用有機培養土”が、プランター栽培に最適です。
市民農園
畑や田は、農地法で取り扱い方が定められており、非農家の人が農地を利用するには様々な制約があります。
市民農園では、市区町村や農協、農家から区画を借りて、比較的自由に、安い費用で、市民が農作物をつくることができます。
家庭菜園では難しい、比較的広いスペースを確保でき、実践の場として最適です。
自分の区画を借りて、本格的な野菜作りに挑戦することができます。
市民農園の特徴
・費用が安い:年額5,000円未満〜1万円程度
・利用面積は、一区画あたり10~30㎡が一般的です。
・契約は1〜2年単位、更新できず期間終了で返却が必要な場合が多い。
・比較的自由に農作物を栽培することができますが、果樹、水稲、樹木など、一部、制限もあります。
・農具・資材・栽培計画は自分で用意するのが一般的です。
・サポート(指導員や講習会など)は原則ありません。
・申込みは年1回が多く、抽選になることもあります。
・募集資格が地域住民に限定される場合が多い。
なお、市町村が運営するものに比べ、農協・農家が運営するものはいろいろな特徴があります。
(開設主体によっては、希望する場合に栽培指導を受けることができる農園もあります。)
市民農園の利用方法
各市町村や農協(JA)のホームページ、インターネット検索などで空きを確認して申し込みます。
農林水産省のホームページで全国の市民農園リストを見ることができるので、近隣の農園を探すことができます。

市民農園の注意点
👉知識や経験が必要
市民農園は費用は安いのですが、サポートは基本的になく、農具の準備や栽培の管理まで
すべて自己管理となるため、ある程度の知識や経験(あるいは協力してくれる経験者など)が必要となります。
👉雑草など管理が必要
特に、管理に手間がかかり、水やりや草取り、害虫対策などの手入れが必要です。
夏場などは雑草が生えやすく、定期的に手入れをしなければ畑が荒れてしまうこともあります。
利用にあたっては、雑草を繁茂させないよう注意する必要があります。
👉距離、交通手段
市民農園は自宅から離れた場所にある場合、週末や休みの日に通わなければならないとか、
定期的に足を運ぶことができないと、作物がうまく育たないこともあるので注意が必要です。
水やりや収穫のタイミングを事前に確認し、効率よく作業を進める工夫が必要です。
👉道具や資材の準備と管理
市民農園では、基本的に自分で道具や苗、肥料などを用意する必要があります。
事前に必要なもの、手順を準備し、自分の道具は自分で管理しなければなりません。
👉マナー
市民農園は共有の場所であるため、同じ市民農園を利用している人たちと交流しながら、
周囲の利用者とのマナーを守ることが大切です。
👉農薬
市民農園では、農薬の使用が認められている農園と認めていない農園があるので確認が必要です。
農薬の使用が認められている農園でも、人畜に危険を及ぼさないように適切に利用し管理する必要があります。
農薬を使用して野菜を育てている人と、農薬を使用せずに無農薬や有機農法で育てたい人が
隣の区画だった場合、農薬の散布により、農薬を使用せずに育てたい人の野菜に意図せずに農薬がかかってしまうなど、農薬使用に関するトラブルとなってしまう可能性があるので注意してください。
また、作物により使用可能な農薬は決まっており、使用不可の作物にかからないように注意することも必要です。
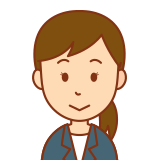
行政が管理する市民農園は農薬の使用がOKなケースが多いですが、
この後、紹介する民間が運営する「レンタル農園」では農薬の使用がNGなケースが多いようです。
市民農園で収穫した作物の販売
市民農園で収穫した作物の販売については、自家消費量を超える分の農産物に関して認められています。(出典:農村振興局農村政策部農村計画課都市農業室)
しかし、販売を目的とした栽培を禁止している市民農園もあるため、農園ごとに確認が必要です。
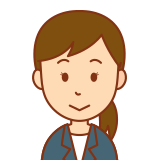
市民農園での栽培は、基本的には趣味や生きがいを目的とします。
予定よりも、たくさん収穫できることもありますが、
基本的には、自分や家族、友達などにおすそ分けし、
利益を目的とした市民農園の利用は控えたほうがよいと思います。
「レンタル農園」(貸し農園)
民間企業が運営するサポート付き「レンタル農園」は、
初心者でも安心して始められるサービスが充実しています。
民間のレンタル農園は、市民農園より費用はかかりますが、
農具、設備や資材が揃っており、
専門の菜園アドバイザーが常駐しているため、野菜作りの基本から指導してもらえ、わからないことをその場で相談できる環境が整っています。
また、他の利用者との交流を楽しむことができるため、一人では続けられるか不安な方でも安心です。

特徴
・農具・資材・種苗・肥料などすべて完備
・サポート体制充実。アドバイザーが常駐、講習会やイベントも開催
・初心者歓迎。経験がなくてもすぐ始められる。
・継続利用しやすく、抽選不要で長期利用も可能
・トイレ、休憩所などの設備が整っている。
・原則、農薬の使用はできないケースが多い。
随時募集・ネットで申込可
費用は一般的な市民農園より高く(年額5万〜10万円程度)なりますが、サポートや手軽さが大きい。週末だけの利用や親子での農園体験にも向いています。
中でも、全国で展開されていて利用者も多いのが、「シェア畑」と「マイファーム」です。
家庭菜園をもっと楽しく!初心者におすすめのレンタル農園
「野菜づくりをやってみたいけれど、庭や畑がない…」「道具や土の準備が面倒…」そんな方にぴったりなのが、レンタル農園です。
必要な道具・苗・肥料は揃っており、菜園アドバイザーのサポートも受けられるので、初めてでも安心して始められます。
育てる野菜
育てやすい野菜を選びましょう!
初心者の方は、トマトやピーマン、葉物野菜など管理がしやすく、コストも安く、比較的失敗の少ない野菜から始めるのがおすすめです。
その中から、興味のあるものを選び、その作物の育て方について調べていきます。
果樹は、木を植えて実ができるまで年数がかかり、木から育てるものはむずかしいです。
お米は、広い田んぼが必要になります。
(ベランダで、バケツに土と水をはって1株なら可能ですが、バケツ3個で茶碗1杯程度)
おすすめの野菜(関東地方以西)
コンテナ栽培でおすすめの野菜を紹介します。

| 野菜名 | 植えつけ時期 | 収穫期 | 植えつけから収穫まで | 特徴・ポイント |
|---|---|---|---|---|
| ミニトマト | 4月中旬〜5月 | 6月〜8月 | 約60〜70日 | 育てやすく、実がたくさんなる。風通しの良い場所が向いている。 |
| ナス | 4月下旬〜5月中旬 | 6月〜9月 | 約70〜80日 | 水をたっぷりあげるとよく育つ。夏の暑さにも強い。 |
| ピーマン | 5月上旬 | 6月〜10月 | 約60〜70日 | 長く収穫できる。実が苦くなりにくく食べやすい。 |
| エダマメ | 5月中旬〜6月 | 7月〜8月 | 約60〜70日 | 日当たりが大事。朝採りすると風味が良い。 |
| オクラ | 5月中旬〜6月 | 7月〜9月 | 約60〜70日 | 暑い時期に元気に育つ。やわらかいうちに早めに収穫するのがコツ。 |
| ラディッシュ(はつか大根) | 3月〜5月、9月〜10月 | 植えつけ後 約1か月 | 約20〜30日 | すぐに収穫できて失敗が少ない。初心者におすすめ。 |
| サヤインゲン | 4月〜6月 | 6月〜8月 | 約50〜60日 | つるがのびるタイプと、のびないタイプがある。支えを立てると育ちやすい。 |
| カブ(小カブ) | 3月〜5月、9月〜10月 | 植えつけ後 約1〜1.5か月 | 約30〜45日 | 寒さに強く、白くて丸い根と葉の両方を食べられる。 |
| ルッコラ | 3月〜6月、9月〜10月 | 植えつけ後 約1か月 | 約30〜40日 | ごまのような風味のある葉野菜。プランター向き。 |
| チンゲンサイ | 3月〜5月、9月〜10月 | 植えつけ後 約1〜1.5か月 | 約40〜50日 | 葉も茎も食べられる。少しずつ間引いて食べてもOK。 |
| ジャガイモ | 2月下旬〜3月(春) 8月中旬(秋) |
6月(春) 11月(秋) |
約90〜100日 | 深めのコンテナで育てるとたくさん収穫できる。 |
| サツマイモ | 5月中旬〜6月 | 9月〜11月 | 約120〜140日 | 少ない水でも育つ。葉も元気に広がる。 |
たいていの野菜はタネから栽培することが可能ですが、
トマト、ナス、ピーマンなど育苗(タネをまいて、植えつけに適した大きさの苗に育てること)の期間が長い野菜はたいへん手間がかかります。
ホームセンターなどで苗(なえ)を買ったほうが便利で、失敗も少なくてすみます。
よい苗から栽培を始めると、生育がスムーズで多くの収穫が期待できます。
病気等に対して強い品種に改良した苗もあります。
なお、ジャガイモは「タネいも」、サツマイモは「さし穂」と呼ばれる茎から育てます。
📝まとめ
家庭菜園でも、自然との触れ合い、日々の変化を楽しみ、新しい知識の習得、家族とのつながりなど、多くの豊かさをもたらしてくれます。
そこには、育てる楽しみや、成長の驚きや喜びがある一方、
枯れてしまったり、虫に食われてしまったなどの失敗もたくさんあります。
そういった失敗も含めて楽しんでいけます。
そして、自分で育てた新鮮な野菜を食べたときは感動しますし、
野菜一つ育てるのがこんなに大変なんだという実感と感謝の気持ちがわいていきます。
野菜作りを楽しみ、収穫の喜びを感じながら、
健康的で心豊かな生活を送ってみてはいかがでしょうか。
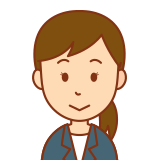
熱中症対策、紫外線対策や腰痛対策など、体調に気をつけて、
くれぐれも無理しないようにしてください。



コメント