私たちの行動の約45%は習慣で成立っているそうです。
その習慣は、はじめは人が習慣をつくり、それから習慣が人をつくります。
そんな重要な「習慣づくり」
バカバカしいくらい小さな行動にして、カンペキに習慣化・自動化されるまで毎日くり返し、定着させてみましょう!
目次
『小さな習慣』
原書名『Mini Habits』
(スティーヴン・ガイズ著 田口未和 (翻訳) 2014年)
よい習慣を、長く続けるためのもの
”小さすぎて失敗すらできない”ものなので、気軽に取り組むことができ、継続できる。
目標は、ばかばかしいぐらい小さくしろ!ということ。
「絶対にやれる」と確信できるレベルまでとことんハードルを下げてみよう!というのが「小さな習慣」の基本です。
ハードルが低いので、普通だと嫌がる脳の抵抗も低いうえ、
目標を立ててそれを達成するというのは、どんなに小さな目標でも気分がよくなり、継続していく好循環が始まりやすくなります。
小さな習慣の大前提は、効果よりも行動を重視することです。
「小さな習慣」とは、毎日これだけはやると決めて必ず実行する、本当にちょっとしたポジティブな行動です。
こんなに簡単でいいの?と思うくらいの課題を自分に与え、それをほんのわずかな意志の力を使って実行するというものです。
目標や習慣をばかばかしいくらい小さくし、その代わりに習慣化(自動化)されるまで毎日、実行する。毎日続けるうちに習慣として定着します。
つまり「とにかく続けること」です。
人生を変えた「腕立て伏せ1回チャレンジ」
私は床に手をつき、1回腕立て伏せをしました。そして、それが私の生活をがらりと変える1回になったのです。
著者のスティーヴンが小さな習慣のアイデアに目覚めるきっかけになったのは「腕立て伏せ1回チャレンジ」だったといいます。
それまで彼は運動を習慣化しようと10年も努力してきたそう。しかしいつもことごとく失敗してきました。
「30分の運動は、私にとっては目の前に立ちはだかるエベレストでした」と彼は語ります。
そんなときに、なかば開き直りのように始めたのが「腕立て伏せ1回チャレンジ」だったのです。

最初のアクションが一番むずかしい
習慣化はロケットのようなもの。
ロケットの最初の上昇エネルギーは、それから後の何万キロも航行するためのエネルギーを上回るのと同じように、習慣化もするのも、最初の立ち上げがもっとも大変で労力がかかります。
そこで”バカバカしいほど小さなステップ”を踏むことによって、最初の抵抗を外すことができます。
たしかにそれは小さな一歩かもしれませんが、1回と0回では天と地ほどの差があるのです。
スティーヴンは「とりあえず腕立て伏せ1回…」と運動をはじめたのですが、
オーケー、あと1回、オーケー、あと2回、そう、もう1回だけ、といった感じです。簡単すぎるくらいの目標を目の前にぶら下げて少しずつ先に進むのです
すると、無事にその目標をクリアできるだけでなく、それ以上こなせることもありました。
ただし、もちろんそんな日ばかりではなく、ベッドのなかで1回だけ腕立て伏せをした日もあったそう。
このベッドのなかの1回について彼は「これほどたやすく目標をクリアでき、記録をとぎれさせずにすんだことが驚くほどの快感」だったと言います。
また、とにかく毎日つづけて習慣化にこぎつけるという上でも、このベッドのなかのたった1回の腕立て伏せが、とてつもなく重要な意味をもったのです
こうして1日に数回の腕立て伏せをつづけたスティーヴンは、着実に筋力をつけていきました。
半年後にはジムでのトレーニング習慣へと発展させることができたのです。
新しい習慣づくりにかかる日数は平均66日
2009年の『ヨーロピアン・ジャーナル・オブ・ソーシャル・サイコロジー』誌に掲載された研究によると、行動が習慣になるまでにかかる日数は平均66日かかるそうです
ただし、66日というのはあくまでも平均値。実際には18日〜254日と大きな個人差があったそうです。
しかし確実にいえるのは、あなたがもし1つの習慣を60日間つづけてきたとしたら、61日目は1日目よりずっと簡単になっているということです。
たとえまだ完全に自動化された習慣になっていなくても、続けている限り着実に成功へのステップを歩んでいるのです。
習慣はすぐに身につかないと同時に、すぐに消えてしまうものでもありませんので、「小さな習慣」の積み上げをがんばっていきましょう!
わずかな意思の力とモチベーション
『小さな習慣』では、モチベーション(※)をあてにするな!といいます。
それは、モチベーションが「感情」だからです。
モチベーションが感情だということは、体調が悪かったり、疲れていたりするとカンタンに浮き沈みしてしまい、自分ではコントロールしづらいわけです。
「よし、今度こそやるぞ!」と最初はやる気いっぱいでがんばるんだけど、モチベーションは続けているうちに下がっていき、1ヶ月後には「モチベーションが上がらない」と言ってやめてしまうでしょう。
モチベーションはもらえるとうれしいボーナスみたいなもので、助けにはなることはありまが、それを基盤としてしまうととても不安定だということです。
小さな習慣では、わずかな意思の力を使い、モチベーションの欠点を補います。
わずかな意思の力とは、小さすぎて失敗できないような小さな習慣を実行に移してくれるほんのわかな力です。
どれだけ疲れていても「やる」と判断すればやれるレベルのことを、日々淡々と積み上げていきましょう。
👉モチベーション(※)
※モチベーション
英語で「motivation」は「motive(動機や目的)」と「action(行動や働き)」で、直訳すると「目的に向かう行動」です。
モチベーションとは、人が目標に向けて行動するための原動力、エンジンのようなもので、日本語で「動機」「やる気」「意欲」などといわれます。
小さな習慣を実施するステップ
小さい習慣とプランを選ぶ
・身に付けたい習慣をリストアップする
・選んだ習慣に対して、とる行動をばかばかしいほど小さくする
※4つ以上の習慣をやろうとしたり、全部で10分を超えるような習慣はおすすめできない。
小さな習慣の基本は、こんなに簡単でいいの?と思うくらいの課題を自分に与え、それをほんのわずかな意思の力を使って実行するというものです。
その習慣を選んだ理由を明確にする
自分の選ぶ習慣が努力に値するかどうかを知るいちばんの方法は、なぜその習慣を選ぶのか、その理由を明らかにすることです。
(例)
👉筋トレ:まったくない筋肉を少しでもつけたい
👉読書:エンタメとして楽しみつつ、知識も身につけて実生活に役立てたい
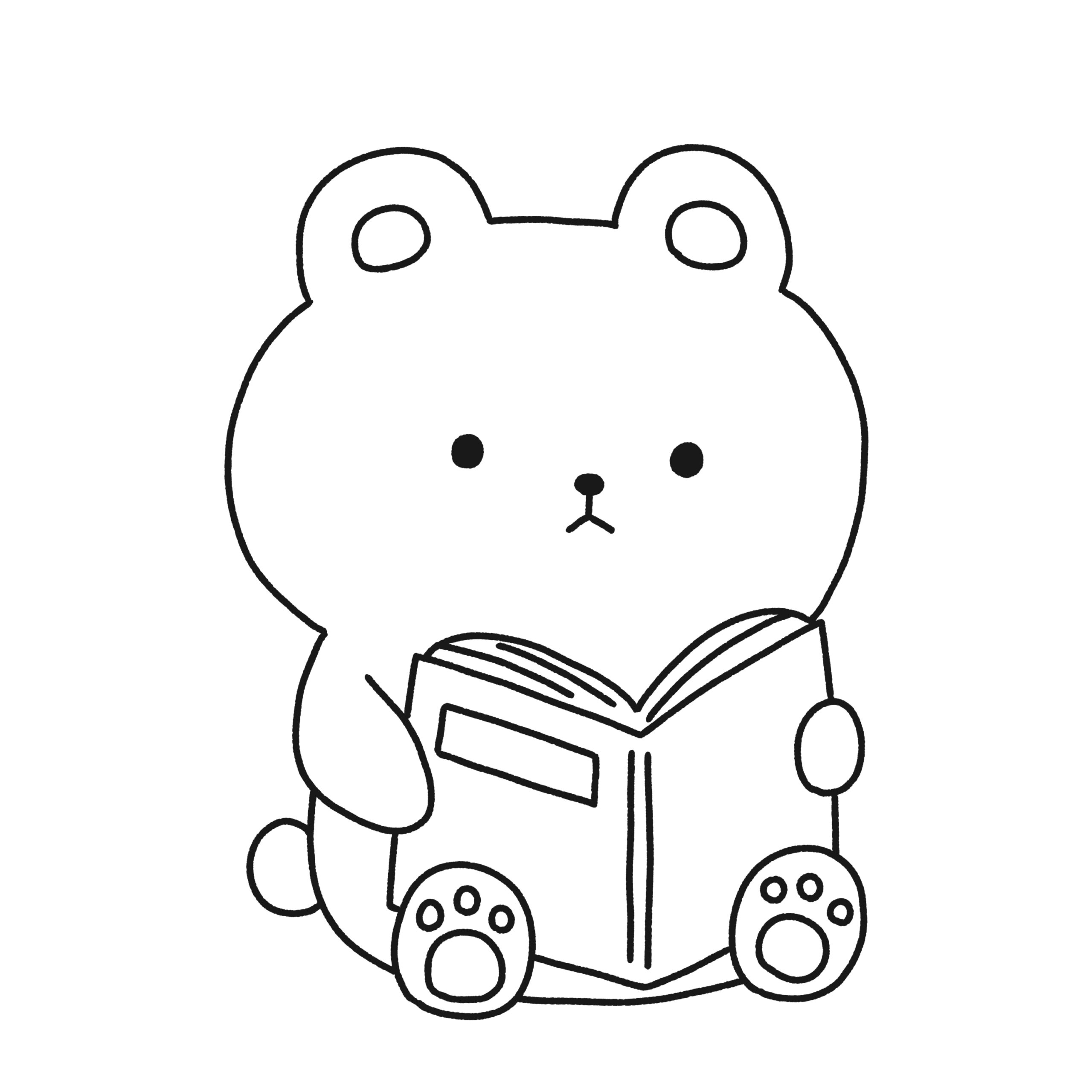
行動開始の合図を決める
小さな習慣の行動開始の合図で一般的なのは、時間ベースのものと行動ベースのものです。
時間ベースの場合には、たとえば「私は月・水・金の午後3時にジムで運動する」と決めます。
行動ベースなら、「月・水・金の昼食を食べ終わってから30分後に、ジムへ運動しに行く」と決めます。
ただ、小さな習慣は、合図なしでもできる小さな行動なので「1日の好きな時間にする」でもいいのです。
報酬を考える
報酬の例として「筋トレしているときだけネットフリックスを見てもいい」といった、直接、脳に働きかける方法がありますが、それを経験している間だけしか効果は続きません。
「筋トレで筋肉が大きくなることが気持ちいい」とか「自分がこれまで達成してきた習慣を確認できるカレンダーのチェックマークを見て快感にひたる」といった、より高度な報酬になると、習慣として定着しやすく、満足度も高いのですが、そこまでいくには少しは時間がかかるので、
最初のうちは直接、脳に直接、働きかけるような報酬にすることからはじめることになります。
すべてを書き留めておく
すべての考えは、紙に書くことで意識の中で重要性が高まるそうです。
進歩を見える化するために、すべて記録にとっておかなければなりません。
「小さな習慣」をとぎれさせるものは、「忘れてしまった」というものです。
失敗することなどありえない「小さな習慣」を忘れないため、カレンダーなどの紙に書いても、スマホのアプリでもいいので、書き留めるか、毎日チェックすることが絶対に必要になります。

小さな習慣を失敗させないルール
決してごまかさない
小さな習慣をごまかす方法はいくつかあります。
最もよくあるのは、「一日に腕立て伏せ1回」などの小さな習慣を選んでおきながら、こっそりもっと多くの回数を自分に求め、「満足感が得られないから、なんとなく10回ぐらいに設定している」という状況です。 目標は「1回」です。
目標以上の成果を自分に課すたびに、それを達成するための意思の力が必要になるからです。
強い抵抗を感じたときは、後戻りして小さく考える
習慣化したい行動に強い抵抗を感じたら、とにかく”バカバカしいほど小さなステップ”に立ち戻りましょう。
小さな習慣の大前提は、効果よりも行動を重視することです。
とにかく続けてさえいれば、結果は後からついてくるので、続けられないくらいならステップを下げましょう。
どれほど簡単な課題か思い出す
まだ「プライドが邪魔をして受け入れらていない場合」
この方法がどう考えてもばかばかしいと思うなら、それはあなたが自分ならもっとできると思っているからです。
どんなに大きな目標も実際には小さなステップで構成されています。
ステップが小さすぎると考えず、ステップが小さいからこそ継続できると、気楽にはじめてみましょう。
小さくとも、昨日、一昨日と比べると確実に前進しているのは事実です。
あまったエネルギーは”おまけ”。目標自体は大きくしない
「バカバカしいほど小さな行動」といっていますが、エネルギーが有り余っていて、腕立て伏せを20回くらいしたい日もあるかもしれません。
そんなときは気の済むまで腕立て伏せをやってしまいましょう。
ただし、目標を大きくしてはいけません。
あくまでも目標は小さな行動にとどめておき、エネルギーが余っているときは、”おまけ”として使いましょう。
もちろん小さな習慣は「腹筋1回」「英単語1個」くらいのレベルでOKです。
そして、そんなレベルではさすがに成長できないのでは?という疑問については、著者は次のように答えています。
まず、小さな課題をこなした後に、ほとんどいつも“おまけ”でもっと多くをこなせます。
これは、私たちがすでにポジティブな行動を望んでいて、一旦始めてしまえば、やりたくないと抵抗する気持ちも弱まるからです。
つまり「腹筋1回」といいながら、実際にやりだすとそれ以上にやってしまう“おまけ”を期待しているわけです。

筋トレをジムに入って始めるのは、お金もかかるし抵抗があったので、家で小さな習慣として始めることにしました。
腕、下半身、腹筋を鍛える筋トレをそれぞれ一つ選び、一日に全部やるのではなく、毎日一つ、腕→下半身→腹筋の順番に繰り返し行っています。
手帳に、昨日は☑腕、今日は☑下半身…と、チェックしています。
ダンベルが必要な時は水を入れたペットボトルを使って、テレビを見ながらやって、終わるとお菓子をつまむ、といったやり方です。
ガリガリなのですが、多少、気のせいか、筋肉がついたような気がして、小さくても達成感を感じはじめています。
まとめ
『小さな習慣』とは「あまりに簡単なので、しないよりする方がいいと思える行動」です。
いくら大きな目標をかかげても、行動が伴わなければ意味はありません。
実際にやれないと自信を失うのでむしろマイナスの方がおおきくなります。
少しだけでもする方が、何もしないよりずっと価値は大きいのです。
さらに、『小さな習慣』は、気分に関係なく課題を実行できます。
普段、毎日、歯をみがく人が、歯磨きとおなじように、『小さな習慣』を気分に左右されず淡々とこなせます。
成功や失敗など気にせず、「試す」気持ちで「わずかな意思力」を使い「小さく」始めていけばいいのです。
『習慣を続けていくうちにやめられない脳になる』
「腕立て伏せ1回」のように、習慣化したいことをできるだけ小さくすることにより、脳がそれを苦痛に感じなくなり、それを毎日やることで達成感が得られ、いつしかやらないと気がすまなくなる。
小さくてもとにかくまず習慣化してしまいさえすれば、1回の行動は小さくても積み重なり確実に実力も自信もついてきます。
それはやがて「大きな習慣へと成長する」ことも期待できます。

自分の良い習慣化の実践のため、自分の中の整理も含めて、『小さな習慣』をご紹介しました。
もっと詳しい内容など、興味を持たれれば、一読されてはいかがでしょうか。
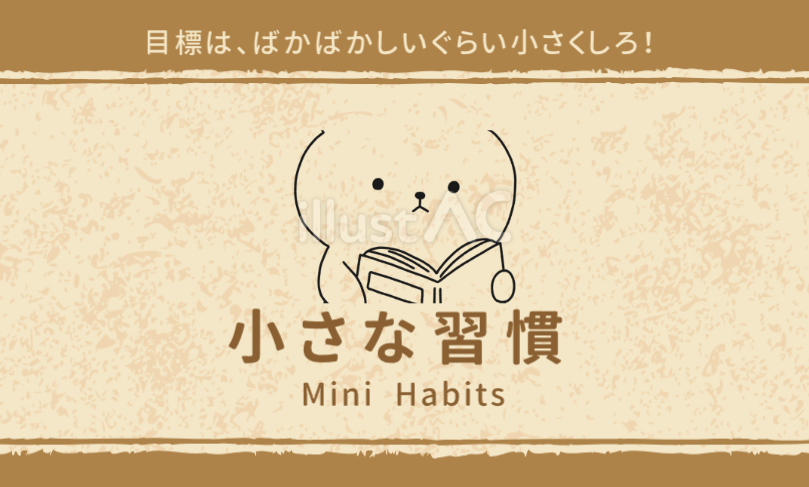
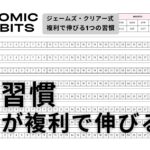
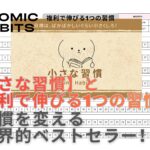
コメント